- 「持続可能な社会実現」のために機械機器・装置のものづくりができるか不安・・・
- 「持続可能な社会実現」のために機械機器・装置のものづくりの現状の課題が分からない?
- 「持続可能な社会実現」のために機械機器・装置のものづくりの課題に対する解決策を教えて!
持続可能な社会実現に近年多くの関心が寄せられています。例えば2015年に開催された国連サミットにおいては2030年までの国際目標SDGs(持続可能な開発目標)が提唱されていますが、持続可能な社会実現のための機械機器・装置のものづくりに向けた課題があります。
持続可能性(sustainability)とは環境・社会・経済などが将来にわたって適切に維持・保全され、発展できること。
私は機械技術者として25年以上働いており技術士一次試験にも合格しておりますが、機械技術者の立場から持続可能な社会実現のために機械機器・装置のものづくりの業務改善が急務と考えます。
そこでこの記事では、持続可能な社会実現のための機械機器・装置のものづくりに向けた課題を挙げ、解決策を提案します。なお課題の分析にあたってはSDGsの次の①~③の視点に着目しています。
- ①経済の視点(生産性向上、科学技術イノベーション)
- ②社会の視点(国土強靭化の推進・防災、質の高いインフラ投資の推進)
- ③環境の視点(省・再生エネルギーの導入、気候変動対策、循環型社会の構築)
この記事を参考にして「持続可能な社会実現のための機械機器・装置のものづくり」に向けた課題と解決策が理解できれば、技術士二次試験に合格できるはずです。
<<「持続可能な社会実現のための機械機器・装置のものづくり」に向けた課題と解決策について今すぐ知りたい方はこちら
持続可能な社会実現のための検討課題
持続可能な社会実現の必要性

持続可能な社会実現に近年多くの関心が寄せられている。2015年に開催された国連サミットにおいては2030年までの国際目標SDGs(持続可能な開発目標)が提唱されており、持続可能な社会を実現する重要性が増している。
持続可能な社会実現をするための課題

機械技術全体から課題を抽出する検討項目を挙げて課題を分析する。
(なお、課題分析にあたっては「2021年版 ものづくり白書」を参考とした。)
- ①デジタルトランスフォーメーション(DX)の取組深化(経済の視点)
効率的かつ戦略的なDXの取り組みを進めていくことが課題である。なぜなら、製造事業者においてDXの取組は未着手又は一部での実施にとどまっているからである。我が国では、目指すべき社会の姿として「Society 5.0」を掲げ、2017年3月には我が国の産業が目指すべき姿として「Connected Industries(コネクテッドインダストリーズ)」のコンセプトを提唱し、世界に向けて発信している。また、製造業をめぐる「不確実性」の高まりに対しては、ダイナミック・ケイパビリティの強化と、そのためのデジタルトランスフォーメーション(DX)の有効性を2020年版ものづくり白書においても提唱されている。
補足)ダイナミック・ケイパビリティとは、デビッド・J・ティース・UCバークレー校ビジネススクール教授により提唱された、戦略経営論における学術用語。2020年版ものづくり白書では、環境変化に対応すべく組織内外の経営資源を再構成・再結合するための能力として、このダイナミック・ケイパビリティを取り上げた。 - ②サプライチェーンの強靭化(社会の視点)
サプライチェーンの強靭化が課題である。なぜなら、世界的な感染症の流行や、世界情勢の悪化等の影響で資材の調達、物流などのサプライチェーンに支障をきたし、供給面に影響を与えているからである。今後も世界的「不確実性」の高まりが想定され対策を打つ必要がある。 - ③カーボンニュートラル(脱炭素社会)の実現(環境の視点)
カーボンニュートラルの実現に向けて取組みを推進していくことが課題である。なぜなら世界各国がカーボンニュートラルに舵を切る中で、我が国としても2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指すと宣言している。このため、エネルギーの安定供給の確保や環境保全への配慮を行う必要がある。
持続可能な社会実現をするための最重要課題と解決策
最重要課題の抽出
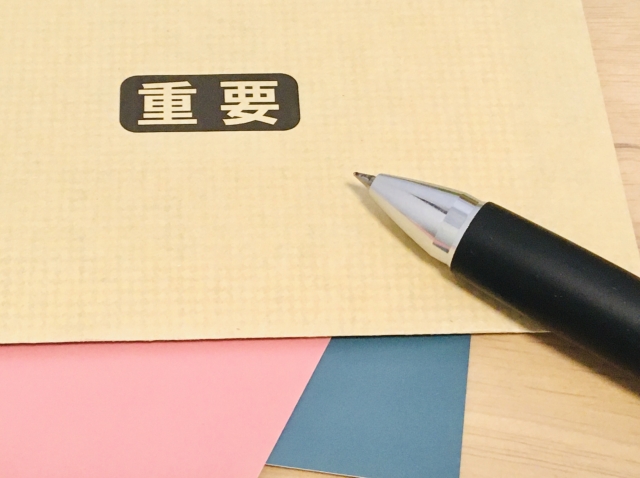
分析した課題の中で「③カーボンニュートラルへの対応」が最重要であると判断した。なぜなら、カーボンニュートラルへの対応は目的とする持続可能な社会を実現するするための根幹であるからである。
解決策

- a)リサイクル設計の推進:
カーボンニュートラルな社会を実現するためには廃棄物等の発生抑制、再使用、リサイクル等を積極的に行う必要がある。このため、リサイクル設計の活用を推進する。リサイクル設計を推進し、製品の構造の単純化、使用材料の統一性、解体、分解の容易性に配慮することで 廃棄物等の発生抑制ができる。 - b)環境配慮設計の推進:
カーボンニュートラルな社会を実現するためには設計段階において3R(Reduce、Reuse、Recycle)に加えて環境配慮設計を行う。具体的には「破棄物処理の容易性」や「省エネルギー」も検討する。これにより環境負荷をより一層低減することができる。 - c)ライフサイクル設計(LCD)の推進:
カーボンニュートラルな社会を実現するためには製品製造に必要な資源を大幅に削減する必要がある。このためLCDの活用を推進する。LCDの活用により「製品ライフサイクル設計」、「製品設計」、「プロセス設計」、「ライフサイクル評価」を適切に行うことで使用する資源の大幅な削減が期待できる。
解決策の共通リスクと対策
解決策の共通リスク

昨今は多様なニーズのある中、多品種少量生産が行われているため、製品製造の初期段階の作業の大部分は設計の上流に集中している。これに加え、上記2.2の解決策を実施することで、更に設計者の負担が増えてしまうリスクがある。
共通リスクへの対策

設計者の負担を軽減する方法として過去の設計データを有効に活用することが挙げられる。しかし、過去の膨大な設計データの中から本業務に活用できる有用なデータを人力で探すには労力と時間がかかる。そこで、PDMシステムを活用する。PDMシステムは大量の設計データの統合管理をするもので、検索システムにAI(人工知能)を利用する。AIの画像認識機能を利用することで類似図面等の検索も容易になる。これにより、設計作業の効率化が図れ、設計者負担が軽減される。
業務遂行における必要要件

技術は日々進歩しているため、リスクについても新たな事象が生まれている。そのため、常に新しい知識を身に付け、それを反映した改良を続けていく必要がある。それでも、リスクが発現する可能性は全くなくなることはないので、適切なリスクコミュケーションが実施できる技術者として、倫理観や社会責任を果たす姿勢が求められる。
補足)リスクコミュニケーションとはリスク分析の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研究者、その他の関係者の間で、情報および意見を相互に交換すること。(厚生労働省HPより)
まとめ
以上
最後まで読んで頂きありがとうございます。
「機械設計」に関する他の記事も多数ありますので是非ご覧ください。
皆様のキャリアアップを応援しています!!
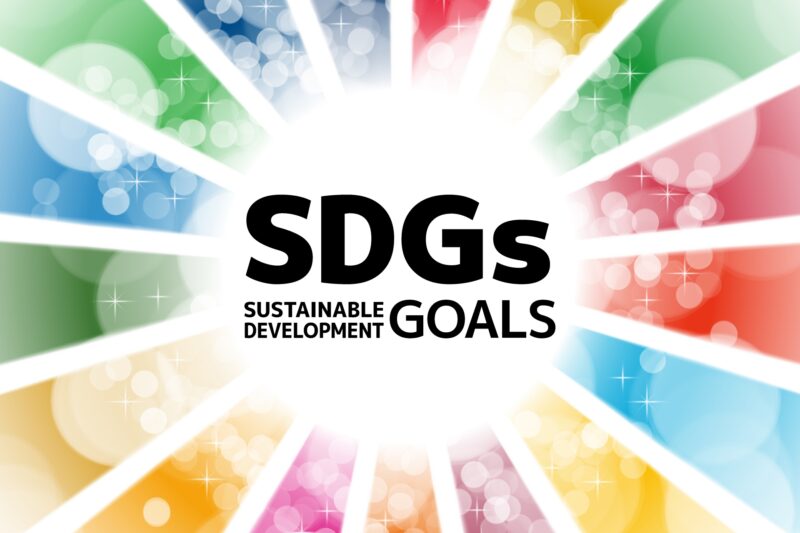
コメント