- 「擦り合わせ」から「組み合わせ」への転換に不安があるけど・・・
- 「組み合わせ」への転換とは何か分からない?
- 「擦り合わせ」から「組み合わせ」への転換する場合の課題を教えて!
日本が技術的な国際競争力を更に高めていくには、機械製品に高い性能と多くの機能が求められると同時に、ユーザーの使用条件に見合った製品仕様の多様化への対応などが必要となってきます。「ものづくり白書 2018年度版」によれば、製造業が直面している課題として、ものづくりの観点から製品仕様の多様化への対応を実現する1つの考え方として、従来の「擦り合わせ」を中心とした相互依存に基づく手法から、「組み合わせ」を中心とした構成要件に基づく手法へ転換が挙げられます。
私は機械技術者として25年以上働いており技術士一次試験にも合格しておりますが、従来の「擦り合わせ」を中心とした相互依存に基づく手法に慣れており、「組み合わせ」への変換が本当にできるか不安を感じております。
そこでこの記事では、「擦り合わせ」から「組み合わせ」へ転換する場合に予想される課題を挙げ、その対策を提案します。
なお、課題の分析にあたっては次の①~③の視点に着目しています。
①メーカー側の視点(製造、設置の容易さ等)
②ユーザー側の視点(品質、機能性、利便性等)
③社会の視点(安心・安全、環境、持続可能性等)
この記事を参考にして「擦り合わせ」から「組み合わせ」へ転換する場合の課題と解決策が理解できれば、技術士二次試験に合格することができるはずです。
<<「擦り合わせ」から「組み合わせ」へ転換する場合の課題と解決策について今すぐ知りたい方はこちら
「擦り合わせ」から「組み合わせ」への転換する場合の検討課題
転換の必要性

日本はこれまで、商品の企画開発段階からの「擦り合わせ」を重視し、取引先の高い満足度を得て、存在感を示してきた。しかし、この方法はコストの高止まりや消費市場が何を求めているかといった点を全て取引先に委ねてしまうという恐れがある。「モノ」によって市場にどのような付加価値をもたらすか、という競争となっている状況下では、致命的な欠陥となるリスクがある。特に、「擦り合わせ」を通じて取引先の意向を尊重することによって持続されてきた日本のサプライチェーンにおいては、一部の企業が変革を目指してもサプライチェーン全体の意向が揃わなければ変革が実現されない。その意味で、高い擦り合わせ力や顧客ニーズ対応力といった従来の「強み」が、成長や変革の足かせとなりかねない。(「2018年版 ものづくり白書」を参考)
「組み合わせ」へ転換する場合の課題の抽出

検討項目を挙げて課題を抽出し分析する。
- ①「ユニット」の共通化・フレキシブル化(メーカー側の視点)
「組み合わせ」でものづくりをする場合、ある決められた部品や装置の「ユニット」を顧客ニーズに対して組合せを変えて製品を製造するため、「ユニット」同士が上手く組み合わさるか検討されていなければいけない。このため、「ユニット」はあらゆる部品と組み合わせ可能なように共通部分を作りフレキシブルな構造とすることが課題である。 - ②ユーザー側のニーズを重視(ユーザー側の視点)
「擦り合わせ」を重視した製造プロセスは、コストの高止まりや消費市場が何を求めているかといった点を全て取引先に委ねてしまう。このため、「モノ」によって市場にどのような付加価値をもたらすかという競争となっている状況下では、致命的な欠陥となるリスクがある。ゆえにユーザー側のニーズへ視点を変換することが課題である。 - ③品質の責任が曖昧になる(社会の視点)
擦り合わせをしないため、技術者は分業による専門化となる。このため、全体を調整することが難しく、もし製造段階で製品の機能性に問題が生じた場合、どの部署が責任をもって改善するのか曖昧になる可能性があり、製品の品質を証明することが課題である。
転換する場合の最重要課題と解決策
最重要課題の抽出

抽出した課題の中で「①ユニットの共通化・フレキシブル化」が最重要であると判断した。なぜなら、ユニットの共通化・フレキシブル化の共通化は目的とする「組み合わせ」を中心とした構成要件に基づく手法への転換を実現するするための根幹であるからである。
解決策
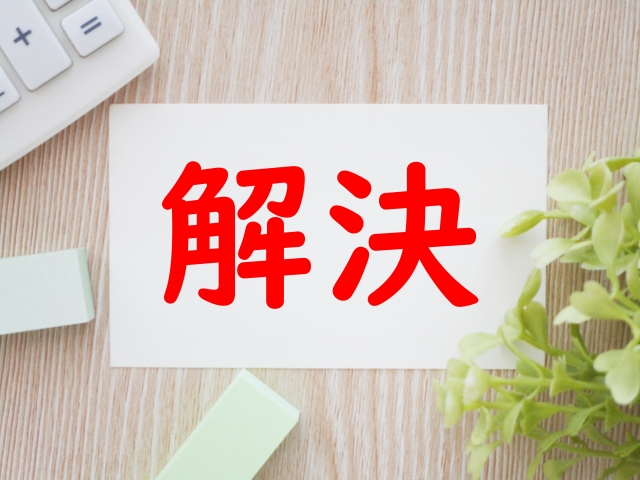
- ①PDMシステムの有効活用
ユニットの共通化を行うためにはまず、大量の設計データをデータベース化し統合管理をすることが必要になる。そこで、PDM(product data management)システムを活用する。PDMシステムを活用できればユニットの共通化に参考となる設計データを整理できる。 - ②設計標準化の推進
ユニットの共通化を行うためには統合管理した設計データをもとに製品設計の適切な標準化を実施する。設計標準化を行うことでユニットの共通化を図ることができる。 - ③設計情報の共有化
共通化をユニットを設計に活かすためにはCADや図面、設計書などの機密性の高いデータを情報共有する必要がある。設計情報を共有すればユニットの共通化を行うことができる。
解決策の共通リスクと対策
解決策の共通リスク

多様なニーズのある中、多品種少量生産が行われているため、製品製造の初期段階の作業の大部分は設計に集中してしまう上に、見直しや再設計の回数が増えるとさらに設計者の負担が増えてしまう。
共通リスクへの対策

設計プロセスにおいて、人工知能(AI)を導入をすることDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する。具体的には次のとおりである。(「AIを機械設計に活用するための課題と解決策とは?」より)
- ①視線検出技術の活用
ベテラン設計技術者の知識・経験(暗黙知)を形式知に変換するにあたり、ベテラン設計技術者が検図中に何に着目しているか視線検出技術により視線の動きを追跡し、データ収集する。そして、その視線の動きを教師データとしてAIに学習させる。このことでベテラン技術者の持つ暗黙知をAIに学習させることができる。 - ②分散深層学習技術を活用
AIを用いて検図を行うためには画像解析処理が必要でこれに膨大な時間が必要である。このため分散深層学習技術を活用し、AIモデルの軽量化・高速化を図る。 - ③画像生成技術の活用
既存の2次元CADデータを3次元CADデータに変換する作業にAIの画像生成技術を活用する。これにより、人手による作業を避けることができ労力と時間を削減することができる。
上記により設計者負担増のリスクへの対策となる。
業務遂行における必要要件
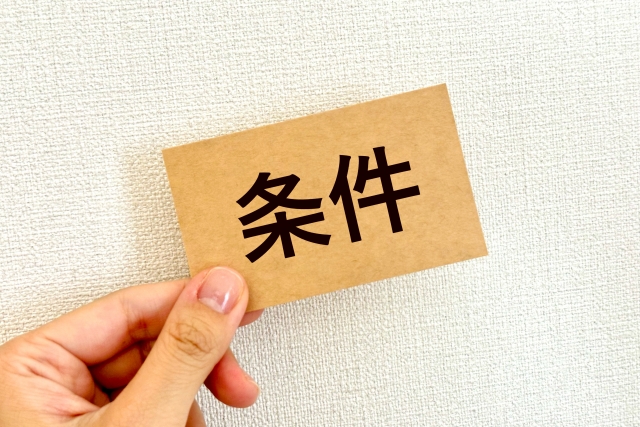
技術は日々進歩しているため、リスクについても新たな事象が生まれている。そのため、常に新しい知識を身に付け、それを反映した改良を続けていく必要がある。
それでも、リスクが発現する可能性は全くなくなることはないので、適切なリスクコミュケーションが実施できる技術者として、倫理観や社会責任を果たす姿勢が求められる。
まとめ
以上
最後まで読んで頂きありがとうございます。
「機械設計」に関する他の記事も多数ありますので是非ご覧ください。
皆様のキャリアアップを応援しています!!
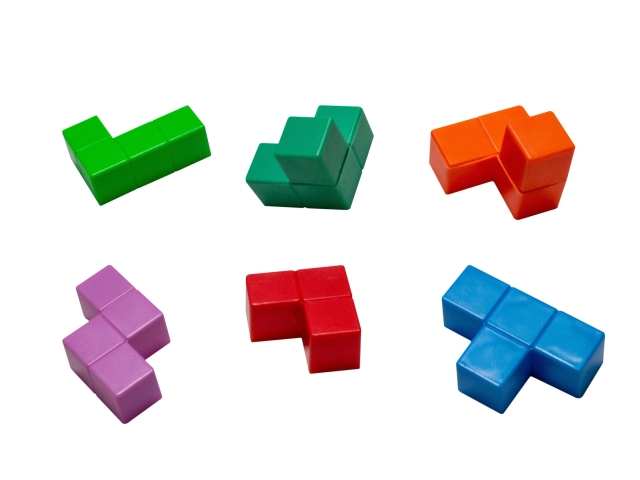
コメント