- 「シミュレーション」を製品設計に用いることに不安があるけど・・・
- 「シミュレーション」を製品設計に用いる際に配慮すべきことがよく分からない?
- 「シミュレーション」を製品設計に用いる際に配慮すべきこと分かりやすく教えて!
昨今、シミュレーションを用いて製品設計されていますが、シミュレーションにおいて現実世界の現象を全て反映することは難しく、シミュレーションを用いる際には配慮が必要です。
私は機械技術者として25年以上働いており技術士一次試験にも合格しておりますが、「シミュレーション」を製品設計に用いることは有効であると考えますが、用いる際は配慮が必要であると考えます。
そこでこの記事では、「シミュレーション」を製品設計に用いる際に配慮すべきことについて解説します。
この記事を参考にして「シミュレーション」を製品設計に用いる際に配慮すべきことが理解できれば、技術士二次試験に合格できるはずです。
<<「シミュレーション」を製品設計に用いる際に配慮すべきポイントを今すぐ見たい方はこちら
目次
実施する場合に配慮すべき項目

シミュレーションとは、対象となるシステムのモデル(模型)を使って模擬実験を行い、問題解決に役立てることを言う。シミュレーションを用いて製品の設計を実施する場合に配慮すべき項目を3つ挙げる。
- ①製品モデルの正確性
- ②製品に加わる外的要因の妥当性
- ③シミュレーション結果の適切な評価方法
配慮すべき項目の具体的内容

上記1で挙げた配慮項目についてその具体的内容を述べる。
- ①製品モデルの正確性
精度の高いシミュレーション結果を得るためには、実機を忠実に反映した製品モデルを構築することに配慮しなければならない。 - ②製品に加わる外的要因の妥当性
精度の高いシミュレーション結果を得るためには、製品に加わる振動、圧縮・引張力、熱等の外的要因を正確に表現することに配慮しなければならない。 - ③シミュレーション結果の適切な評価方法
シミュレーションの結果が本当に信用できるものなのか適切に評価できる方法を策定することに配慮しなければならない。
まとめ
以上
最後まで読んで頂きありがとうございます。
「技術士二次試験」に関する他の記事も多数ありますので是非ご覧ください。
皆様のキャリアアップを応援しています!!
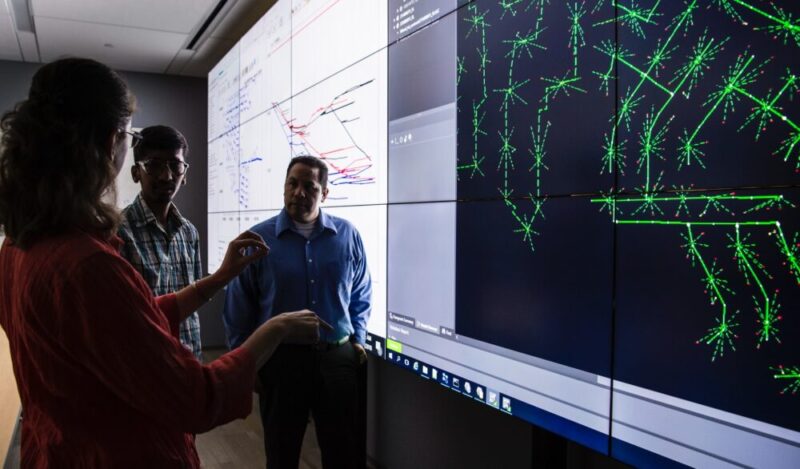
コメント