- インフラ老朽化に不安がある・・・
- インフラ老朽化に対して安全・安心な社会を実現するための課題が分からない?
- インフラ老朽化に対して安全・安心な社会を実現するための課題に対する解決策を分かりやすく教えて!
日本の産業設備は、高度経済成長期に建設されたものが未だに稼働している状況であり、かなり老朽化した設備が見受けられます。例えば、東海道新幹線は開業後、50年を超えています。このような設備の老朽化の対策としては、保守・点検を継続的に実施することで安全性を確保しています。
私は機械技術者として25年以上働いており技術士一次試験にも合格しておりますが、インフラ老朽化に対して対応することは急務であると考えます。
そこでこの記事では、水門設備を例に機械技術者の立場からインフラ老朽化に対して安全・安心な社会を実現するための課題とその解決策について述べます。なお、課題の分析にあたっては次の①~③の視点に着目しています。
①メーカー側の視点(製造、設置の容易さ等)
②ユーザー側の視点(品質、機能性、利便性等)
③社会の視点(安心・安全、環境、持続可能性等)
この記事を参考にして、インフラ老朽化に対して安全・安心な社会を実現するための課題が理解できれば、技術士二次試験に合格できるはずです。
※水門設備とは洪水対策を目的として堤防等に設置されるものです。その構成は扉体、戸当り、開閉装置、付属設備、電気設備です。水門設備の操作は地方自治体から委託された操作員が行うことが多く、近年は操作員の高齢化が著しい状況です。
<<「インフラ老朽化に対して安全・安心な社会を実現する」ための課題と解決策を今すぐ知りたい方はこちら
安心・安全な社会を構築するための検討課題
安心・安全な社会を構築する必要性
日本の社会インフラは、高度経済成長期に建設されたものが未だに稼働している状況であり、かなり老朽化した設備が見受けらる。安全・安心な社会を実現するためにはこれら社会インフラ正常に機能することが求められる。ここでは、社会インフラのひとつである水門設備を例に、設計、維持管理に関する課題とその解決策を複数提示し、提示した解決策に共通する新たなリスクとその対策について述べる。なお、水門設備は洪水対策を目的として堤防等に設置されるもので、その構成は扉体、戸当り、開閉装置、付属設備、電気設備から成る。水門設備の操作は地方自治体から委託された操作員が行うことが多いが、近年は操作員の高齢化が著しい状況である。
水門設備の設計・維持管理に関する課題の抽出
- a)設計に関する課題
製品不具合や使用者の誤操作により故障が起きた後の影響(事故や災害)も考慮して設計する必要がある。このため設計時点でリスクを洗い出し、万が一故障してもその影響を最小限に食い止める対策をあらかじめ講じておくことが課題である。 - b)維持管理に関する課題
既設の水門設備の多くは高度経済成長期の昭和50年代に製造されたものであり、耐用年数 40年を超え 老朽化が著しい。一方で国や地方自治体の財政は厳しい状況であり、正常機能を維持しつつ維持管理費のコストを縮減することが課題である。 - c)更新・修繕に関する課題
効果的な更新・修繕を行うためには、設備の重要度や劣化状況等を考慮した更新・修繕計画の立案をすることが重要である。
維持管理費のコストを縮減するための解決策
最重要課題の抽出
分析した課題の中でb)維持管理費のコスト縮減について解決策」が最重要であると判断した。維持管理費のコスト縮減は目的とする安心・安全な社会を実現するための根幹だからである。
解決策
- a)保守点検の効率化
水門設備の状態監視は、点検時に人力により作業を行うことが多いが、センサーやIoT機器等のデジタル技術を活用しオンラインで自動的に状態監視ができるようにする。具体的には、電動機(開閉機用)の電流、電圧、回転軸の温度等をセンサーにより定期的に計測し、IoT機器により計測データをデータサーバへ補完することで自動化できる。これにより維持管理の省人化、省力化が可能となり維持管理費のコスト縮減が図れる。 - b)安全評価の基準を明確化
老朽化した施設を安全に使用するためには安全性を適切に評価する必要がある。このため、製品ライフサイクル設計での安全性の評価を行う。 - c)長寿命化技術の活用
製品の長寿命化を図る必要がある。
上記の解決策で共通する新たなリスクと対策
状態監視保全に区分した装置・部品について、状態監視の結果が整備・更新が必要ないと判断するものであっても他の整備・更新が必要な装置・部品と一体で整備・更新した場合の方が合理的でトータルコストが安価になる場合がある。例えば開閉装置の巻上ドラムを交換する際にワイヤーロープも交換する場合である。また、事後保全に区分した装置・部品について、整備・更新をする前に製造メーカーが供給を停止をすれば装置・部品の調達が困難になり保全できない危険性がある。このため、事後保全に区分した装置・部品であっても調達可能性を確認し、修繕計画の前倒しを検討する必要がある。
業務遂行上必要となる要件
技術は日々進歩しているため、リスクについても新たな事象が生まれている。そのため、常に新しい知識を身に付け、それを反映した改良を続けていく必要がある。それでも、リスクが発現する可能性は全くなくなることはないので、適切なリスクコミュケーション※1が実施できる技術者として、倫理観や社会責任を果たす姿勢が求められる。
社会インフラである水門設備は、大規模地震においてその機能を十分に発揮しなければならない。このため、老朽化した水門設備について効果的な維持管理方法を提案し信頼性の向上に寄与したい。
※1 リスクコミュニケーションとはリスク分析の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研究者、その他の関係者の間で、情報および意見を相互に交換すること。(厚生労働省HPより)
まとめ
以上
最後まで読んで頂きありがとうございます。
「機械設計」に関する他の記事も多数ありますので是非ご覧ください。
皆様のキャリアアップを応援しています!!
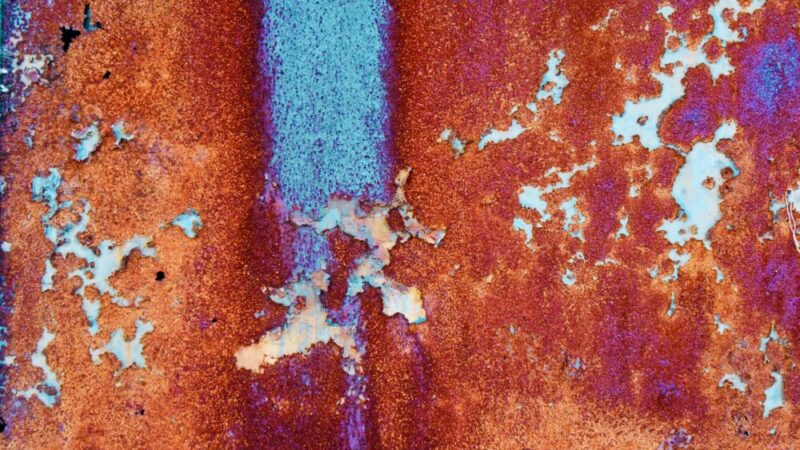
コメント