- 「コストと品質の両立」に不安があるけど・・・
- 「コストと品質を両立」する課題が分からない?
- 「コストと品質を両立」するための方法を分かりやすく教えて!
近年明らかになった「品質データの改ざん」は、これまで高く評価されてきた日本製品への信頼を揺るがしかねない重大な問題でありますが、「コストと品質の両立」に苦労するケースは非常に多いです。
私は機械技術者として25年以上働いており技術士一次試験にも合格しておりますが、「コストと品質の両立」するためには課題がいくつかあると考えます。
そこでこの記事では、技術者の初心者でも分かりやすいよう「コストと品質の両立」をするための課題とその解決策について解説します。
なお、課題の分析にあたっては次の①~③の視点に着目しています。
①メーカー側の視点(製造、設置の容易さ等)
②ユーザー側の視点(品質、機能性、利便性等)
③社会の視点(安心・安全、環境、持続可能性等)
この記事を参考にして「コストと品質の両立」をするための課題と解決策が理解できれば、技術士二次試験に合格することができるはずです。
<<「コストと品質の両立」をするための課題と解決策について今すぐ知りたい方はこちら
現状と課題の分析
現状

現在の経済状況はインフレと円安による物価上昇が著しく原材料の高騰により生産コストが著しく上がっている。一方で生産コスト増を販売価格に転嫁することは競争力の低下を招くため、コスト削減による品質低下が懸念される。このような中、コストと品質の両立をすべく早急な取り組みが求められている。
課題の分析
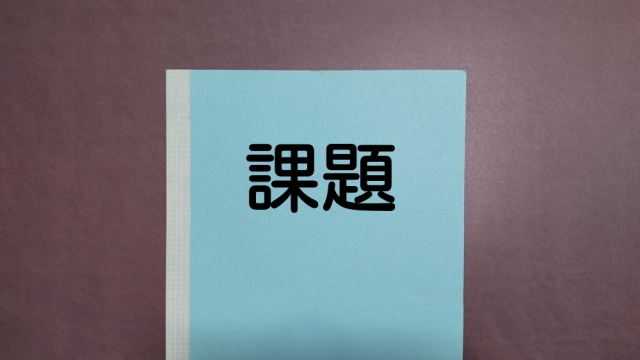
- a)多品種少量生産による製造コストの増大(メーカー側の視点)
多品種少量生産をより効率的に行える生産体制を構築することが課題である。具体的には多品種少量生産においては仕入れコスト、倉庫管理コスト、生産ラインの組替作業が発生し、製造コストが増加する。このため設計、製造、検査のプロセスの効率化に取り組む。 - b)製品の高機能・高性能化による製造コストの増大(ユーザー側の視点)
複雑な仕組みの製品の品質を効率的に確認する検査方法を構築することが課題である。具体的には多様なニーズや安全への配慮により製品が高機能・高性能化した状況であり、製品検査に要するコストが増加する。このため、検査の効率化に取り組む。 - c)環境への配慮による製造コストの増大(社会の視点)
エコデザインにかかるコストを縮減することが課題である。具体的には、昨今、持続可能な社会の実現に向けてエコデザインの実施が求めれ、環境効率を飛躍的に高めようとすると製造コストが増大する。このため、エコデザインに係る製造コスト削減に取り組む。
最重要課題の抽出とその解決策
最重要課題の抽出
抽出課題の中で「a)多品種少量生産による製造コストの増大」が最も重要な課題であると判断した。なぜなら、a)多品種少量生産による製造コストの削減効果が最も大きいためである。
課題に対する解決策

- a)設計の標準化(設計プロセス)
製品設計において、その都度、最初から設計を行うのではなく、設計の標準化を実施しておき設計の効率化を図る。具体的には共通仕様書の作成、共通製品の使用、数量計算書の標準化を行う。これにより、設計プロセスを効率化できる。 - b)製缶作業・機械加工の自動化(製造プロセス)
これまで人力に頼っていた工場内の製品運搬等の作業をロボットに代替させる。ただし、製品の全ての品種を自動化対象とすると非常に複雑かつ大規模な自動化設備となるため、自動化対象の製品を絞り込む。これにより製造プロセスを効率化できる。 - c)検査の自動化(検査プロセス)
品質確保のためには適正な検査は欠かせない。しかし多品種の製品に対して適正な検査を行うには多大な労力を要する。そこで検査の作業にカメラと人工知能(AI)の物体認識技術を活用し代替させる。これにより、検査プロセスを効率化できる。
解決策がもたらすリスクとその対策
解決策がもたらす共通するリスク

上記の解決策はいずれも設備投資に膨大なコストがかかり、もし実施すれば会社経営を圧迫するリスクがある。また、自動化されることでそのプロセスがブラックボックス化し技術伝承が確実に行われないリスクがある。
共通するリスクへの対策
設備投資にかかるリスクについては、経済産業省が行っている「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」や「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」等の支援事業を活用する。また、自動化にかかるリスクについてはナレッジマネジメントを行い技術伝承が確実に行われる体制を構築する。
業務遂行上必要となる要件・留意点
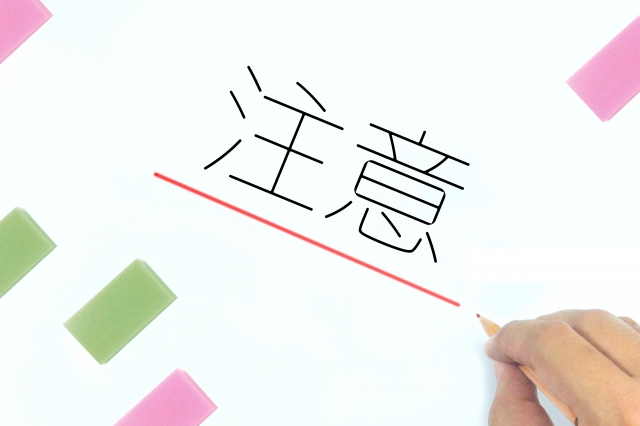
製造メーカーの目的は利益の追求であるが、同時に社会的責任を果たさなければならない。社会的責任とはIOS26000にあるように「持続可能な発展」に貢献することである。このため、機械技術者には将来の世代の人々が自らのニーズを満たす能力を危険にさらすことなく、現状のニーズを満たす努力が必要である。 ゆえに、生産コストを更に削減するだけではなく、高機能素材や低炭素・省エネ製品の開発をすることで地球環境に配慮し、併せて製品の付加価値を高め製品の差異化を図り、市場での競争力を高めることに留意すべきである。
まとめ
以上
最後まで読んで頂きありがとうございます。
「機械設計」に関する他の記事も多数ありますので是非ご覧ください。
皆様のキャリアアップを応援しています!!

コメント