- 「最適設計」の実施に不安があるけど・・・
- 「最適設計」において留意することが分からない?
- 「最適設計」において留意すべきことを教えて!
最適設計は決定すべき主要なパラメータ(設計変数)を選択し、安全性や有用性などを確保するために課せられる条件(制約条件)を満足する領域(許容設計領域)の中で、コスト、機能、重量などの設計の目的とするもの(目的関数)を最適化(最小化あるいは最大化)するような設計変数を決定するような設計を最適設計をいいます。
私は機械技術者として25年以上働いており技術士一次試験にも合格しておりますが、最適設計は機能と品質の両立、及びコストダウンを行う上で重要な手法であると考えます。
そこでこの記事では、「最適設計」を用いるために検討すべき事項について解説します。
この記事を参考にして「最適設計」を用いるために検討すべきことが理解できれば、技術士二次試験に合格できるはずです。
目次
最適設計を用いるために検討すべき項目

最適設計を用いるために検討すべき項目を以下に3つ挙げる。
- ①評価規範の設定
- ②最適設計問題の定式化
- ③最適化手法の選定
検討項目の具体的な取組内容

上記1.検討項目の具体的な取組内容を以下に述べる。
- ①評価規範の設定
目的関数(最適にしたいもの)、制約条件、設計変数を決定する。 - ②最適設計問題の定式化
設計変数から目的関数の値を導く計算モデルを作成する。
(例:表計算ソフト、CAE(Computer Aided Engineering)、実験、数式(関数)) - ③最適化手法の選択
最適化アルゴリズムを選択する。
〈最適化アルゴリズムの例〉
・関数最適化
・確率論的手法
・近似最適化手法
・多目的最適化手法
・ニューラルネットワーク(深層学習)
・品質工学的手法 など
取組を進める際に留意すべき事項

上記2.の取組みを進める際の留意点を以下に述べる。
- ①評価規範の設定
設定した目的関数、制約条件、設計変数が、最終的な設計解の最適性に及ぼす影響は多大である。このため設計者自身の知識や経験だけに頼るのはリスクがあり、知識工学的手法等の活用に留意すべきである。 - ②最適設計問題の定式化
最適設計問題の定式化にあたっては、利用可能な解析や最適化のためのツール群や計算機の能力を視野に入れることに留意すべきである。 - ③最適化手法の選択
最適化アルゴリズムは上記のとおり多くの手法があり、目的に応じた適切な手法を選択する。
以上
最後まで読んで頂きありがとうございます。
「機械設計」に関する他の記事も多数ありますので是非ご覧ください。
皆様のキャリアアップを応援しています!!
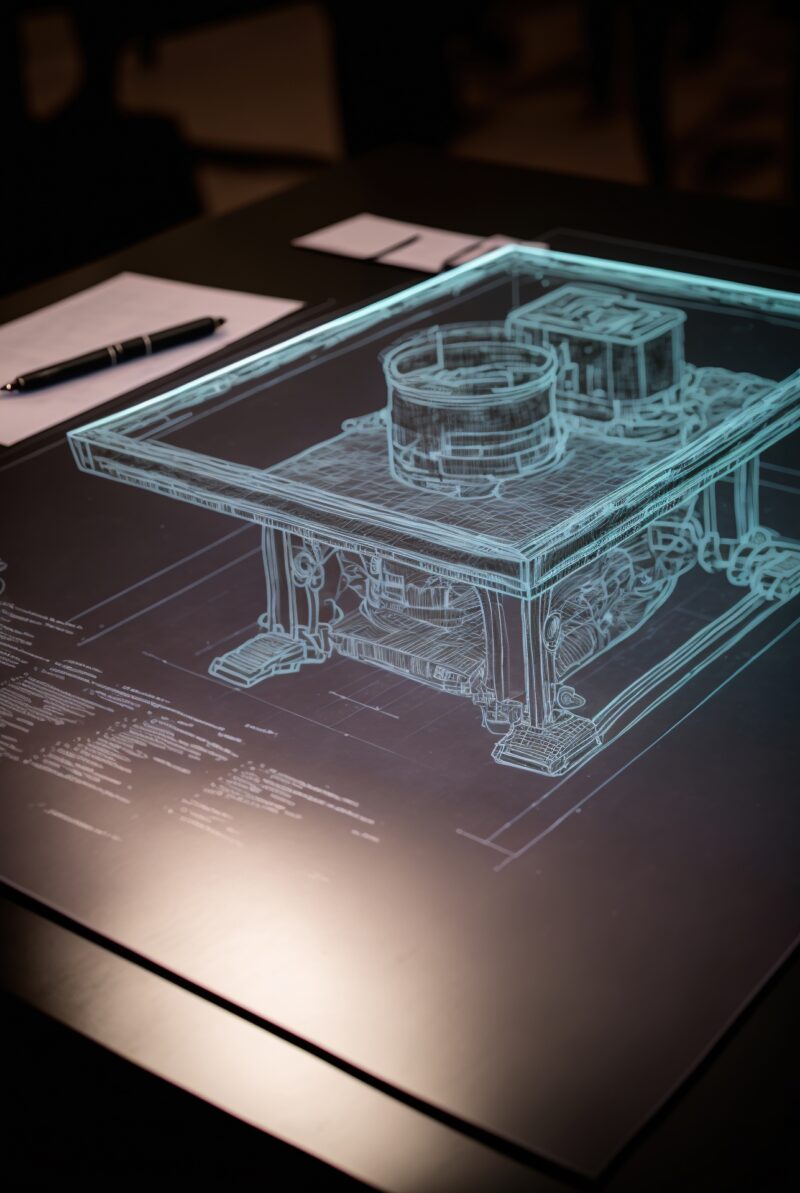
コメント